成人自閉症スペクトラム・発達障害の改善はミュゼアルディ
うつ病と新型うつdepression
うつ病について
 |
 |
 |
ところが時に、原因が解決しても1日中気持ちが落ち込んだままで、いつまでたっても気分が回復せず、強い憂うつ感が長く続く場合があります。このため、普段どおりの生活を送るのが難しくなったり、思い当たる原因がないのにそのような状態になったりするのがうつ病です。
うつになりやすい性格とタイプ
うつ病になりやすい性格は一般的には次のようなものとされています。(いわゆるタイプA)
・生真面目
・几帳面
・仕事熱心
・責任感が強い
・気が弱い
・感情豊かでいつも他人に気を配る
・相手の気持ちに敏感
★誘因となるストレス
うつ病は、さまざまな”過度なストレス”が引き金になると考えられています。ストレスのうちでとくに多いのは、人間関係の変化と仕事環境の変化です。たとえば身近な人の死や、リストラなどの悲しい出来事だけではなく、昇進や結婚、出産といった、本来は嬉しい出来事がきっかけでうつ病になることもあります。
★身体症状などとの関連
慢性の病気の場合はとくに、体の不調や痛み、社会生活の変化、経済的な負担などがストレスとなり、抑うつ症状がみられることがあります。カウンセリングをお受けになる場合や、医療機関で治療を受ける時でも、金銭的負担が限度を超えると、症状が改善するどころか、かえって負担となることも多くあります。
また、服薬が病気だけに効果があればよいのですが、実際には副作用として抑うつ症状が現れるものがあります。ウイルス性肝炎の治療に使われるインターフェロン、抗がん薬、ステロイド、抗潰瘍薬などが、うつ病を引き起こすことがあります。
同じ「うつ(病)」といっても、多くの種類があります。従来型うつ病と新型うつなどはずいぶん違う
症状が表出します。
 |
 |
 |
 |
従来型のうつ(病)は一種の気分障害で、うっとおしい気分が続き、不安・あせり・不眠・食欲低下・
焦燥感などの特徴がある精神疾患です。実際、不安というものは、実際には人間の暴走を防ぐ安全弁の
ような働きもあるのですが、それがやや多いという軽いうつ状態から、希死念慮が強く何度も自殺を図
るという重症例まであります。
従来型うつの代表的症状としては、主に以下の2つがあります。
○抑うつ気分
○興味や喜びの喪失
臨床現場においては、この2つのうちひとつが含まれていること、また2週間以上その状態が継続する
ことが「うつ病」診断基準となっています。
原因としては
・心理的なストレス(仕事・人間関係など)に起因するもの
・統合失調症や境界性パーソナリティ障害など他の精神疾患によるもの
・身体のリズム(体調や生理)や季節/場所などの要因によるもの
などがあげられます。
それに対して、新型うつという言葉は心理学用語ではなく、アダルトチルドレンと同様巷間流布してい
る造語です。医療機関では、患者の治療をする際に「新型うつ」という言葉は使いません。
新型うつは従来型のうつ病ではなく、ほぼ「非定型うつ病」だと考えられています。まったくイコール
だとは言い切れませんが、ほぼそうだと考えられているそうです。(この表現が医療機関的言葉です)
「うつ病」と「非定型うつ病」の典型的な違いは、前者が常時深いゆううつ感が湧いてくるのに対して、
後者の場合は、「本人にとって都合の悪いこと」に対面すると気分が沈み込んだ状態が続くものの、良
ことや楽しい出来事があると、それまでの不調がウソのようにたちまち元気になるということです。
言い方は悪いですが
●仕事のときだけうつ状態が発生する
●休職中も上司や同僚に迷惑をかけているという認識はあまりない
●自分は「うつ」だと公言しても平気
●うつになったのは会社や同僚のせいだと考える
これらの症状を訴える方が増加してきたため、従来のケースに該当しない方を総称して「新型(非定型)
うつ」と称しています。
典型的なパターンとしては、仕事上のストレス(弱いもの)をきっかけに「うつ病」という診断を受け
るケースです。この場合、会社の産業医などでは特に抑うつ気分が(会社に限定されているとはいうも
のの)存在しますから、うつ病という診断を下さざるを得ません。あるいは「適応障害」という診断名
になることも多くなりました。
ところが、本人はいたって元気。休職しても趣味だけは続けたり、旅行に行ったりしていますが、さあ
復帰という問題になれば病状がぶり返すなどグズグズし、有給休暇を繰り返すのです。永遠に休みを取
り続けることはできませんから、いずれは退職することになるのですが。
ですから、そのような状態を見た周囲の方は「サボリ癖」とか「わがまま」とか呼ぶわけです。
心理の専門家ではない人事関係者などには、対応に苦慮するあまりに自分がうつになったりする場合もあ
って、笑っていられないのが現実です。
うつかもしれないと思ったら
自分がうつ症状ではないかと思ったら、なるべく早く精神科・心療内科での治療やカウンセリングを考
えてみましょう。日本では、診断、治療、処方をする事ができるのは、医師か精神科医のみと法定され
ていますので、どこに行ったら良いか判断に迷う場合には先ず医師の診察を受け、自分の状態や気持ち
を話してみて下さい。
 |
 |
 |
単純なお悩み(失恋や一過性のミスなど)では話を聞いてもらっただけで楽になる場合もあるくらいで
す。
一般的には「急性期」(めまいがする・倒れそうだ)というケースでは迷わず医療機関へ。そうでない
場合はカウンセリングルームでもかまいませんが、日本のシステムが「患者(クライエント)が治療法
を選択する」という本末転倒な状態になっていることが問題を複雑にしています。
「うつ」という認識があった場合でも、実際には他の要因が潜んでいることも多く、単にお聞きするだ
けのカウンセリングや、精神を安定させるだけの投薬治療では改善できにくい場合もあります。症状が
重い場合には服薬とカウンセリング等の併用が効果的です。
ミュゼ山手心理相談室では、「うつ」などというお客様の申告にかかわらず、本質的な状態を総合的に
お聞きしていきます。あまり症状が重くなってからお越しの場合は、お話をお伺いすることさえも難し
くなりますので、対応できません。なるべく早期にお越しいただけるよう、ご家族の方なども含めて対
応をお考えください。
特に新型(非定型)うつと従来型うつは区別する必要があります。
「★ちょっとだけ興味が出てきた・・・・かも★」という方は
○06(6180)6280
へお電話いただくか、または
○メールでのご予約
をしてみましょう。 (≡^∇^≡) ご連絡をお待ちいたしております。
山手心理相談室のうつ改善プロセス
一般的なうつ(病)やアダルトチルドレンの改善カウンセリングでは、
★まず最初に、お悩みの点をじっくりとお聞きします。もちろん人によって生育歴や現在の症状や環境
は異なりますので、あくまでご自身の主観でお話しいただきます。
★つらい経験や思い出をお話しいただいたら、今後の改善・回復方法を説明し、押し付けではなく一緒
に考えていきます。
★今までご両親との信頼関係がなかったわけですから、改善に当たってはカウンセラーとの間にラポー
ル(信頼関係)を構築することが大切です。小さな問題であっても、ひとつひとつ一緒に確認しながら
決めたり、確認したりしていきます。その工程を繰り返していくうちに、自信をもって主観を語ること
ができるようになっていきます。(新型うつは傾向が違います)
★回復カウンセリングの過程で、ご自身の”癖”に気づくと思います。その癖を一つ一つカウンセラーと
考え、改善していきます。
ところが、発達障害を持つ方の場合は、このように進めることは不可能です。カウンセリングそのもの
の意味合いが理解できなかったり、話の輪郭を把握できないことがその原因といえます。単純なうつ病
の場合はある程度定型的な手法により対応可能なのですが、発達障害の方には個別対応が必要です。
山手心理相談室にお越しの方の場合、うつと発達障害やアダルトチルドレンの症状が併発している方が
とても多いです。新型うつ自体の定義があいまいなので
発達障害+二次障害としてのうつ=新型うつ
とは言い切れませんが、近いものだとお考えください。山手心理では通常のうつ回復カウンセリングと
並行して発達障害やアダルトチルドレン改善のSSTを行っています。
この症状の場合、うつが悪化する傾向にありますので、通常うつよりさらに早期の対応が望まれます。
 |
うつ病と日常生活
うつ病も他の病気と同じように、治療せずに放置しておくと徐々に悪化していきます。ですから、症状が軽いうちにうつ病に気づき、治療をはじめることが最も大切です。気分の落ち込みがあらわれる少し前に、生活の中で楽しみを感じなくなった、何をしてもおもしろくない、日常生活のさまざまなことに興味を失った、集中力がなくなってきた、物事の決断ができなくなったなど症状の兆候があらわれることがあります。
また、うつ病が進行すると仕事や日常生活にさまざまな支障をきたすようになります。 たとえば
「買い物に行っても、何を買ったらよいのか決められない」
「パソコンやテレビの電源を入れるのが面倒くさい」
「お風呂やシャワーなんてしなくても死なない」
「部下からの書類に判を押しても良いのか決められない」
「悲しくて寂しくてじっとしていられないので、誰かにそばにいてほしい」
など、仕事や家事の能率も上がりません。
悪化すると動作が鈍くなったり、強い不安、焦燥感からイライラと周囲に当たり散らしたり、ソワソワと落ち着きなく動き回ったりすることもあります。仕事や家庭がうまくいかないのは自分のせいだと思い込み、さらに落ち込みます。
その結果、自分に自信をなくして仕事をやめてしまったり、ひとりになりたいために離婚してしまったりします。もっと悪い状態になると、うつ病の症状によるつらさから、いっそこのまま消えてしまいたい、死にたいと思うほど追いつめられてしまう(希死念慮)こともあります。
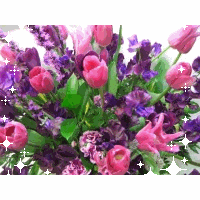 |
 |
